外食で吐き気がするのはなぜ?克服の為にすべきこと3選
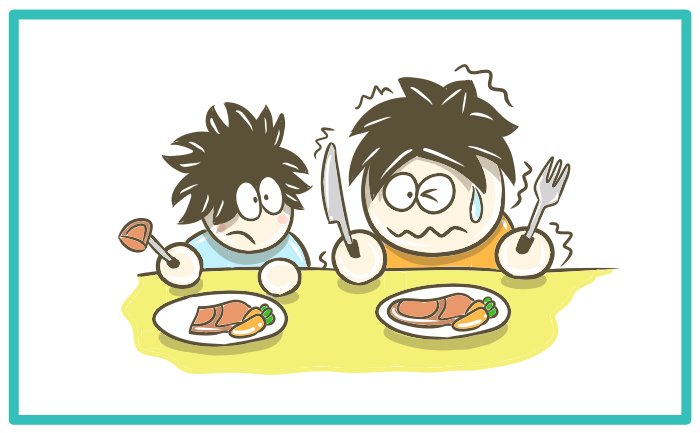
「外食で吐き気がして食べることができない」「緊張して全く喉を通らなくなる」 カウンセラーの私のもとにはこうした相談がたくさん届きます。 この記事をご覧になっているあなたも、このようなお悩みを抱えていませんか?
私もかつてこれらの症状に大変悩んでおりました。他人との食事は緊張するので苦手という方は多いですが、その緊張が度を越してしまい、食事を楽しむどころではない症状に悩まされている方がいらっしゃいます。
本記事ではこの外食・会食で吐き気がするのはなぜか?とその背景にある「会食恐怖症」「嘔吐恐怖症」、そして克服するためにまずすべきこと3選 を解説していきます。本記事で最短で克服に向けての第一歩を踏み出すことが出来ます。
- 外食で吐き気がする原因「会食恐怖症」「嘔吐恐怖症」
- すべきこと:嘔吐恐怖症を正しく知る
- すべきこと:病院に行くべきかを見定める
- すべきこと:段階的な認知行動療法をやっていく
この記事の内容
外食で吐き気がするのはなぜ
最初に外食で吐き気がする仕組みについて解説します。理由はすごくシンプルで、「過緊張」の状態に入ってしまうからです。適度な緊張はパフォーマンスの発揮に必要ですが、それが過剰になると体に様々な反応を引き起こします。吐き気もその反応のひとつです。
極度の緊張に襲われた時に、吐き気が起こってしまうのは「誰でも」です。これは特異な体質だからという訳では無く、人間の生理学的な反応が原因だからです。これは「闘争・逃走反応」 と呼ばれるものです。
これは吐き気だけに留まりません。震え、喉のしまり、胃のキリキリとした痛みなど食事で起きる不快な症状は、全てこの生理現象が原因なのです。
吐き気するのは「闘争・逃走反応」が起きるから

「闘争・逃走反応」は私達の体に元来備わっている、人間が危機に瀕した時に発動する防御メカニズムです。
私達生物は何か自分の身に脅威が迫った時、その脅威を排除するために闘うか、それとも脅威から逃げ出すかの選択をしなければなりません。そして闘うにせよ逃げるにせよ、身体はそれに備える必要があります。脅威が迫ると「闘争・逃走反応」が起こります。闘う・逃げるといった⾏動が素早くできるように、心拍数を上げて筋⾁に⾎流を巡らせます。
緊張するとドキドキして、冷や汗かきますよね︖これは脳が脅威に対して体を闘争・逃走モードにしているからです。よく「火事場の⾺⿅⼒」なんて言いますが、あれは本当に「闘争・逃走反応」によって普段よりも⼒が出るようになっているのです。
身に脅威が迫った時は「闘争・逃走反応」は役⽴つものです。しかし闘う・逃げることに体のエネルギーを集中できるよう、他の不要不急の機能は全て停止してしまうのです。特に「食べる」という行為は身に脅威が迫った時に最も不要な行為なので、食べることに関わる機能は全部停止してしまいます。唾液はでなくなり、喉はしまり、胃はうまく広がらず少し痙攣した状態になってしまいます。これがやがて吐き気につながるのです。
「緊張して食べられなくなるのは私だけ︖」と考えていた方もいるかもしれません。しかし緊張して「闘争・逃走反応」が起きている時に食べられないのは当たり前です。体が食べ物を受け入れる状態でないのですから。気持ちの問題ではなく、物理的に食べることが難しくなっているのです。
そして私達にとっての脅威とは外食・会食といった苦手な場面なのです。こういう場面に対峙すると、過去の経験から「食べられなかったらどうしよう」「気持ち悪くなったらどうしよう」という不安が生まれます。その不安に注意が向き続けると、やがて不安が大きくなり恐怖に変わります。すると脳が「身に脅威が迫っている!」と判断して、「闘争・逃走反応」が起きてしまうのですね。
このような外食の度に闘争・逃走反応に襲われ、食事を楽しめない状態、これを「外食恐怖症」「会食恐怖症」「嘔吐恐怖症」と言ったりします。
症状は吐き気、めまい、胃痛、嚥下(食べ物が呑み込めない)、緘黙(黙り込んでしまう)、嘔吐など様々です。特に「吐いたらどうしよう!」という嘔吐への恐怖が強い場合「嘔吐恐怖症」と呼んだりもします。会食の度にこうした症状が出てしまうので、次第に会食を避けるようになります。ここでは吐き気と関連のある嘔吐恐怖症に名称を統一して使っていきます。
これまで嘔吐恐怖症は精神的な疾患の一つであるにも関わらず、あまり知られた存在ではなく、病院でも積極的な治療の対象とはなっていませんでした。私自身、嘔吐恐怖症で心療内科を受診したときは「気にしないでください」の一言で済まされてしまいました。そのため「こんな症状自分だけ・・・」と誰にも相談できずに、一人で抱え込んでしまいがちです。
ですが嘔吐恐怖症は自覚したその時から、まずやっておくべき重要なポイントが3つあります。この3つを最初におさえておくと、克服までの時間をグッと早めることができます。
すべきこと:嘔吐恐怖症を正しく知る
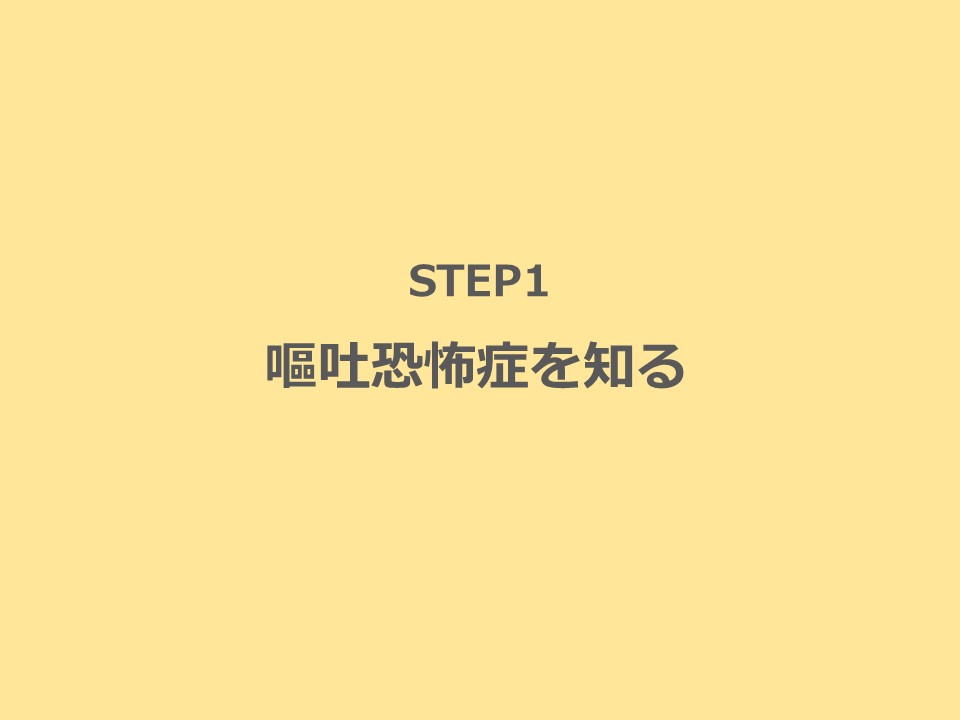
まず最初にすべきことは「嘔吐恐怖症を正しく知る」です!当たり前のようですが、おろそかにしてしまう方は結構います。「自分は嘔吐恐怖症かどうか分からないグレーゾーンだと思う。病気についていろいろ調べてしまったら、余計に病気に意識が向いて悪化するのでは?」という理由で、敢えて何年も知ろうとしない方もいます。
しかしこれはあまりオススメ出来ません。確かに病気について調べを重ねると、一時的には余計に病気に意識が向いてしまうことはあります。一時的にネガティブな感情になってしまうことはあります。しかし結果的には克服に向けての正しい知識と行動力が身に着きます。
嘔吐恐怖症の自覚が少しあるけど、それを放置して自然に治癒することはあまり期待出来ません。(一般的な不安障害の3年後自然治癒率は3割程度です) 特に嘔吐恐怖症は後述の認知行動療法が必要になってくるので、ますます放置での治癒は期待出来ません。
まずは積極的に嘔吐恐怖症の知識を身に着けて下さい!私の配信や本サイトの情報が非常にお役に立つと思います!何よりも最初に嘔吐恐怖症を正しく知ることが重要です。
そして嘔吐恐怖症の症状だったり、治療法だったりと表面的な病気の概要について知るだけでは十分ではありません。それに加えて
- 嘔吐恐怖症はよくある病気である
- 嘔吐恐怖症になるのは普通のことである
と知ることも、さらに重要です。
嘔吐恐怖症で怖いのはその症状だけではありません。症状に伴う不安や自己批判により「嘔吐恐怖症に悩んでいるのは自分だけだ」「自分のメンタルが弱いからいつまで経っても治らないんだ」という間違った思い込みが強化され、どんどん治りにくい意識になってしまうことです。
こうした不安や自己批判は最初に取り除かなければいけません。でなければ嘔吐恐怖症の克服も人生を良くするきっかけではなく、自分だけの欠点を治す作業という位置付けになってしまい、行動のモチベーションも高まらないからです。
嘔吐恐怖症はよくある病気であると知るには、同じ症状を持つ仲間と交流することが一番効果的です。最近はSNSで嘔吐恐怖症について発信したり、オフ会など開いたりしている方もいます。私のコミュニティでも定期的にオフ会を開いています。
最初は嘔吐恐怖症についてポジティブな情報を発信しているカウンセラーをフォローしていくのがオススメです。 さらには積極的にコミュニティに参加して、もしくは自分で作って交流を深めるのもオススメです。
すべきこと:病院に行くべきかを見定める
自分が病気かもと自覚したら、まず病院に行くべきかが気になりますよね。私が推奨する判断基準は以下になります。
自分が嘔吐恐怖症という自覚はある。でも会食等のある一定の場面以外は、日常生活は問題なく遅れている。生活に支障が出るほどの不安では無い。自分が苦手な場面に挑戦すれば、症状が改善している実感もある。改善には前向きである。
このような場合なら、病院に行く必要はありません。後述しますが既に自分で前向きに認知行動療法に踏み出せている状態ですね。一方で、
自分が嘔吐恐怖症という自覚はある。日常の様々な場面に不安があり、生活に支障が出ている。日常の不安感が強く目の前の事に集中できない。改善している実感が全く無い。
このような場合なら、病院に行って薬を処方してもらうのも良いでしょう。どうしても症状が辛い場合は薬も適切に活用すべきです。薬で症状を抑えながら、どうやって改善していくかを相談してみましょう。
しかし後者の場合であっても、嘔吐恐怖症を正しく取り扱えない病院に行く場合は、あまりオススメは出来ません。
基本的に病院で行われる治療は2種類しかありません。症状が重い場合は抗不安薬などの症状を一時的に抑える薬が処方されます。軽度ならいわゆる「認知行動療法」と呼ばれる治療についての指導をうけます。とても簡単に言えば、外食等の自分が苦手な場面に実際に挑戦して、だんだん慣らしていくという治療法です。嘔吐恐怖症の根本治療にはこの認知行動療法が必要不可欠です。
嘔吐恐怖症を扱っていない病院だと、正しく診断してもらえない可能性もあります。(私が以前に行った心療内科では、嘔吐恐怖症の事を話しても、「気にしないでください」で済まされたこともあります。)さらには適応障害とか自律神経失調症とか別の診断で、別の薬を処方されてしまうこともあります。
病院に行く前にホームページなり、電話なりで会食恐怖症・嘔吐恐怖症を診れるかを確認しておくことが必須になります。もし正しく診てもらえる見込みのない病院に行くくらいなら、オススメはできません。(私自身間違った病院選びは色んな苦い経験があります。。。)
そうなると「近くに嘔吐恐怖症を診てくれる病院が無い!」と心配になる方もいると思います。でも大丈夫です。薬を処方することを除けば病院の主な役割は、認知行動療法の指導になります。 認知行動療法の方法は私のコンテンツで学んで頂ける内容でも十分かと思います。(実際に私が病院で受けた説明の内容を、わかりやすくお伝えしていますので)
つまりは病院の有り無しに関わらず、自分で認知行動療法を重ねていくことが必要不可欠です。
すべきこと:段階的な認知行動療法をやっていく
嘔吐恐怖症への正しい知識を身に着け、病院を活用できるようになったら、段階的に認知行動療法をやっていきましょう。
外食に苦手意識をもってしまった人は、もう外食を楽しめないかと言えば、もちろんそんなことはありません。人の意識は環境や行動によって少しづつ変化していくものです。一生固定されるものではありません。
ではどのように克服すれば良いのでしょうか?外食に行かずに苦手意識が無くなることはありません。一番確実な方法は、自分が挑戦できる範囲で徐々に外食に挑戦していく、徐々に楽しめるようになっていくことです。
これは認知行動療法と呼ばれるもので、嘔吐恐怖症だけでなく様々な不安障害に対して効果を上げている治療法です。自分が苦手な場面に敢えて挑戦して慣れていくことで、根本的な治癒が期待できます。
認知行動療法に取り組む中で、徐々に過去の外食や会食に対するネガティブな記憶が書き換えられ、過緊張状態になることなくリラックスして食事を楽しめるようになります。
認知行動療法はいきなり本格的に取り組む必要はありません。最初は本当に小さなステップでも効果があります。外食ができないなら、「お店の前まで行って、美味しそうに食べている自分をイメージする」これも立派なステップのひとつです。認知行動療法について詳しく知りたい方は以下もご覧ください。
おわりに
本記事の内容をまとめます。
- 外食で吐き気がする原因は過緊張。過剰になると「嘔吐恐怖症」に
- すべきこと:嘔吐恐怖症を正しく知る
- すべきこと:病院に行くべきかを見定める
- すべきこと:段階的な認知行動療法をやっていく
本記事では外食での吐き気の原因と、その背景にある「嘔吐恐怖症」、そしてまずすべきこと3選について解説しました。嘔吐恐怖症の場合は初動対応が特に重要です。早くに正しい知識を身に着けて、病院も活用できて、認知行動療法に踏み出すことが出来れば、克服までの距離をグッと短くできます!
本サイト「嘔吐恐怖症克服カレッジ」では今後も外食恐怖症・会食恐怖症・嘔吐恐怖症の克服に役立つ情報をお届けしていきますので、お楽しみに。それでは最後までお読みいただきありがとうございました。
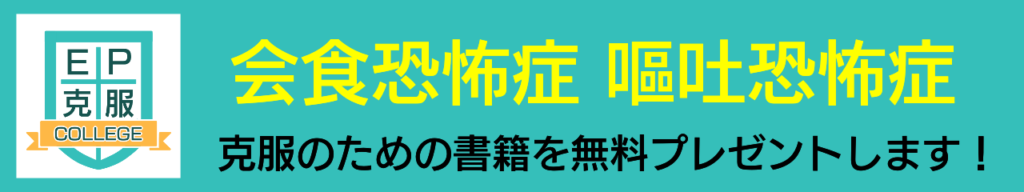
かずおかず@会食恐怖嘔吐恐怖克服LINEでは、克服お役立ち情報の配信・克服支援サービスの提供・LNE限定イベントや企画のご案内を行っています。登録された方に、吐くのがこわい会食恐怖症と嘔吐恐怖症の克服お役立ち電子書籍【『吐くのがこわいにさよならする ~嘔吐恐怖症を克服する人が知るべき3つのこと~』】(119P) 無料進呈中!
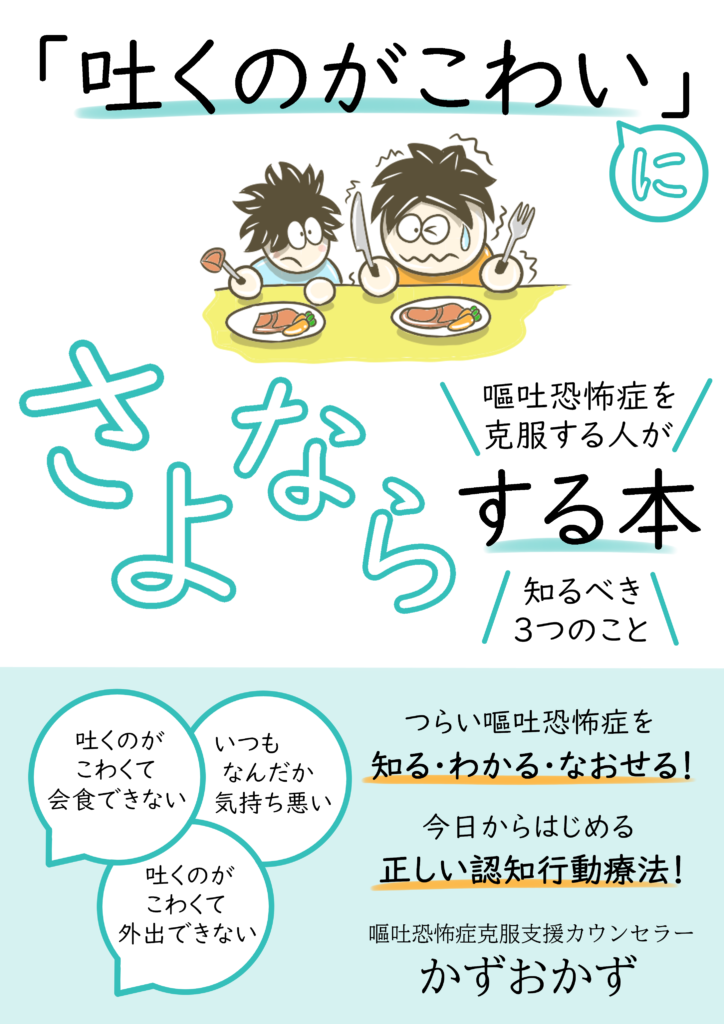
【かずおかず@会食恐怖嘔吐恐怖克服LINE 登録はこちらから!】





