
今回は不安を緩和する方法についてお伝えします。嘔吐恐怖症は常に不安と共にあります。その症状自体がつらいことはもちろんですが、それに加えて不安がつらいです。
- 慢性的な不安
- 予期不安
慢性的な不安とは、病気が将来に及ぼす影響に対する不安です。当時の私は嘔吐恐怖症がひどく、一日三回食べることもままなりませんでした。そして将来に対する不安に常に悩まされることになりました。
- 大人なのにご飯も食べられないなんて…
- 誰に相談すればいいの?
- こんな状態で体調は大丈夫か?学業を続けていけるのか?
- 将来就職とかちゃんとできるのか?
こうした不安が日常の中でひっきりなしに襲ってきます。そのせいで学業も遊びもバイトも何もかも手がつかない状態でした。楽しいはずの学生生活のほとんどは、こうした不安に苦しめられる時間で終わってしまいました。
そして不安はこれだけではありません。いざ会食の練習に行こうとすると襲われる予期不安もあります。予期不安は会食などの予定が決まった日から
当日まで続きます。私も海外旅行に行くと決めた時はその日から一か月ほど、ずっと予期不安に苦しめられました。
- 全然食べられなかったらどうしよう
- もっと会食が嫌いになったらどうしよう
- みんなに嫌われたらどうしよう
こうした不安は認知行動療法に取り組む上で大きな障害となります。
不安はなくせない

当時を振り返ってみると、私はこのような不安に対して本当に振り回されるばかりでした。
周りの大人や病院に相談しても「気にしすぎでしょ」と言われるばかり。そして気にしないように頑張るほど不安が大きくなる悪循環でした。ですがこんな状況に陥ってしまうのも当然です。不安への正しい対処法を全く知らなかったからです。
当時はこんな風に考えていました。
- 不安を感じるのはそれ自体異常なことだ
- 練習で自信がつけば不安はなくなる
これらは不安にまつわるよくある誤解です。不安というものはなくせません。不安感情は人間が生き残るために一番必要なものとして、進化の過程でどんどん発達させてきたものだからです。
不安がなくなれば人間はあっという間に滅びます。私たちは普段その恩恵に感謝することはありませんが、生活が成り立っているのは全部不安のおかげなのです。でも不安がなくならないなら、この苦しみも一生続くのでは?と思いますよね。
でもそうではありません!不安はなくせませんし、常に存在しているものです。ですが、不安との向き合い方を変えていけば、不安から受けるネガティブな影響を大きく減らすことができます。
これはちょうど部屋の隅で、動く黒いものを見つけた時の状況と似ています。最初は「何だろう!ゴキブリだったらどうしよう!!」とパニックになりますよね。ですがよくよく見ると、ただゴミが風で動いていただけだったりします。ゴミはずっとそこに存在しているのですが、一度正体を知ると気にしなくなりますよね。
不安もこれと全く同じです。不安というものを客観視して、その性質がわかってくるほどに気にならなくなるのです。
不安を客観視する
不安は常に存在しています。毎日数えきれないほどの不安が私たちを襲います。そこで私たちはいちいち真剣に取り合って不安をなくそうとする(なくせませんが)よりも、不安を客観視して、不安の影響を減らすトレーニングをする方が有益です。
不安を客観視するというのはどういうことでしょうか?それは以下のような思考の切り替えを即座に行うことです。
不安を信じ込んでいる状態
「明日の会食不安だな。全然食べられなかったらどうしよう。もう会食に行けなくなる。みんなに嫌われる。」
不安を客観視している状態
「明日の会食不安だな。今自分は不安を感じているんだな。苦手な会食に挑戦するのだから、不安を感じるのは人間として自然なことなんだな。不安は無理になくそうとすると大きくなるから、このままでいいんだな。」
前者の場合は、不安がほとんど現実と信じ込んでいます。そのため不安がどんどん連鎖して大きくなっています。これに対して後者は、不安を感じたという事実を単なる自然な現象として受け止め、それ以上に余計な解釈を加えていません。「今不安を感じた。それは自然なこと」これ以上の解釈をしないので、不安も連鎖しないで大きくなりません。
慣れてくると不安に対して余計な解釈を加えないという態度が自然と身についてきます。不安はなくせないが、それを受け止めると大きくならないことに納得できるようになります。
不安を手放す 6 つのトレーニング
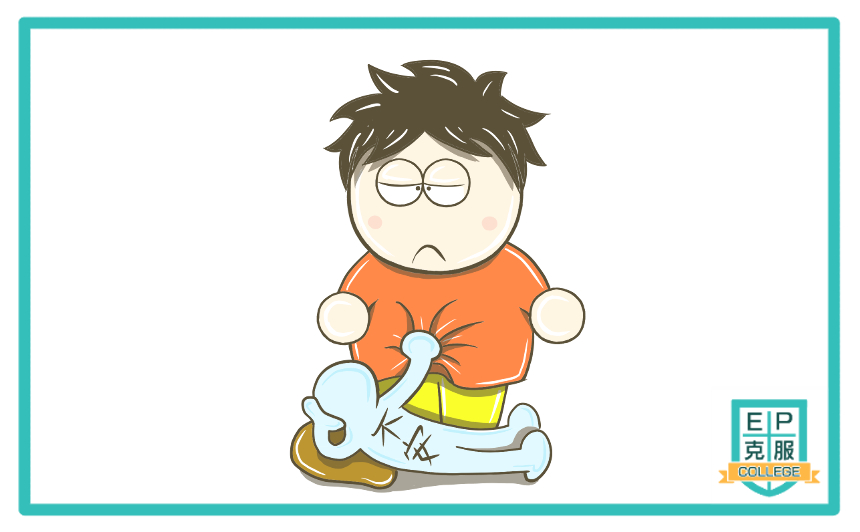
不安を受け流す脱フュージョン
それでは不安を客観視して受け流していくトレーニングをこれから6つ紹介していきます。これらのトレーニングは「脱フュージョン」と呼ばれます。不安を完全になくすことはできません。脱フュージョンもこの原則に基づいており、不安の存在を許すが、それ対していちいち真剣に取り合わずに受け流すトレーニングです。
不安を信じ込みすぎて、どんどん不安が大きくなっている状態を「フュージョン状態」と言います。そこから脱するので脱フュージョンなのです。
さて、これまでOPENERSで学びを深めてきたあなたは既に、不安との向き合い方が変わり始めていると思います。瞑想にも取り組んで来られた方なら既に不安が緩和される効果を感じ始めているかもしれません。
瞑想やセルフコンパッションをやると不安に強くなることは何度もお伝えしました。これから紹介するテクニックは瞑想が習慣化されるまでの補助となるようなテクニックです。
瞑想によって不安に強くなるのは、自分でコントロールしてやるというよりも感覚的に勝手に出来てくるものですので、ある程度継続が必要です。これから紹介する脱フュージョンテクニックはそれよりも即効性があり効果を感じやすいものです。瞑想が習慣化されない間は是非積極的に活用して頂きたいと思います。
脱フュージョンテクニックは色々ありますが、全ての目的は「感情を客観視して、感情から受ける影響を小さくすること」です。瞑想を継続していくと、やがてこれが自然と努力なく出来るようになってくるので、脱フュージョンテクニックを意識する必要もなくなってくるのです。
客観的に言い換える
最初のトレーニングは非常に単純です。例えば「自分はなんてダメな奴なんだ!」と浮かんで来たら即座に「自分は『自分はなんてダメな奴なんだ!』と考えている」と頭の中で言い換えてみましょう。これで不安が自分にとって絶対信じるべき真実から、ただ頭に浮かんだストーリーへと認識が変わります。
こうして「今自分は不安なことを考えていたな」「でもそれ自体は問題ではないのだな」と客観的視点に立てるのです。他にも「自分は『嘔吐恐怖症は治らない』と考えている」「自分は『会食は楽しめない』と考えている」などの言い換えもできるでしょう。
不安は事実ではなくただのストーリー、頭の中だけの想像です。不安の大半は実際には起こりませんし、また起こったとしても自分の想像以上に悪いことであるケースはほぼありません。ですが人間は何も意識しなければ、その不安を過剰に信じ込むように出来ているのです。脱フュージョンをすることで不安を事実ではなく、ただのストーリーであると再認識するのです。
ここでの注意点としては、脱フュージョンをしても不安が消えるわけではないということです。脱フュージョンは不安が大きくなるのを防ぐトレーニングであり、不安が生まれてこなくなるわけではありません。ですが、こうしたトレーニングを続けることの効果は大きいです。やがて不安が生まれても、ただ不安があるという事実だけを受け入れて、不安について考え過ぎることが無くなります。
キャラクターボイスで言い換える
次のトレーニングは自分の好きな映画や漫画やアニメのキャラクターの声で、不安を頭の中で言ってみるという方法です。自分の声で不安なことを言われると信じてしまいますが、別のキャラクターの声だと真剣に受け取れないのです。
これは私のお気に入りの方法で、よく実践しています。「自分はなんてダメな奴なんだ!」と浮かんで来たら、ド〇えもんの声で「君は本当にダメな奴だな~」と言い直します。
声だけでなく、具体的なイメージを思い描いてみるのも良いでしょう。キャラクターが頭の中や漫画やアニメの中で、「君は本当にダメな奴だな~」「もう人生おしまいだね」「嘔吐恐怖症は治らないぞ」など様々にネガティブなことを言ってくる様を思い描きます。
このような自分の感情をキャラクター化してみるというのは、不安に対する抵抗やネガティブイメージを軽減するのに効果的です。他に比べて最初に効果を実感しやすいトレーニングでもあります。
歌で言い換える
こちらのトレーニングはキャラクターボイスに近いですが、不安を頭の中で歌のメロディーにのせて言ってみるという方法です。
歌はなんでも良いですが、よく例に使用されるのはハッピーバースデーのテーマとジングルベルのテーマですね。こちらは誰でも知っている歌ですからね。できるだけ歌のメロディーにそうように、自分の不安をのせて頭の中で歌ってみます。やってみると意外と難しいです。
ハッピーバースデーのテーマなら「自分はダメな奴~」「自分はダメな奴~」「自分はダ~メ~な~や~つ」みたいな感じです。(文面だと全然メロディーが伝わりませんね。。)この不安の替え歌を作るという作業自体が、不安を客観視することになります。
不安の物語にタイトルをつける
あなたの不安もそんなに種類は多くなく、一日に何度も同じ不安が生まれているのではないでしょうか。人間は一度に多くのことを悩めないですから、だいたい一番の不安が一日に何百回・何千回と生まれます。
次のトレーニングはおなじみの不安にタイトルをつけるという方法です。「嘔吐恐怖症はもう一生治らない!」という不安が頻繁にやってくるなら「また『嘔吐恐怖症が治らない』の物語が来たな」と言い換えてみましょう。おなじみの不安には○○の物語、というタイトルをつけてラベリングしておくことで、不安を真剣に取り合わずに客観視することができます。
心に感謝する
次のトレーニングは最も単純です。不安が生まれたら、そのたびに「私の心よ!ありがとう!」と思うだけです。私たちは普段その恩恵に感謝することはありませんが、生活が成り立っているのは全部不安のおかげなのです。不安な感情も私たちの命を守るために一生懸命なのです。
そこで不安が生まれるたびに敢えて心に感謝します。感謝の言葉の他にも「それは本当かい?」「そりゃあすごいな」「それは良い忠告だね」みたいな言葉も良いでしょう。敢えて心に感謝するのは、不安を受け流すだけでなく、不安に敢えて感謝するという感情と真逆の行動をとることで、より不安に影響を受けにくくなるトレーニングにもなります。
6つの口ぐせに注意する
最後のトレーニングでは私たちが特に不安に引き込まれている時に思いがちな6つの口ぐせに注意します。普段膨大な考え事をしていると、何が不安で
何が不安ではないのか分からなくなることもあるでしょう。ですが私たちが特に不安に引き込まれている時に思いがちな6つの口ぐせというものがあります。
この口ぐせに気を付けて、ついつい思ってしまったら、「あ、今不安に引き込まれそうになっているな」と気が付いて、脱フュージョンしていきましょう。以下が6つの口ぐせです。
- どうしてこんな気分なんだ?
- 私が何をしたっていうんだ?
- なぜ自分はこうなってしまうのか?
- 私にはどうにもできない。
- こんな風に感じるべきではない。
- こんな風に感じなければいいのに。
最初の4つは不安に余計な解釈を色々加えてしまっている状態であり、最後の2つは不安をなくすことに固執している状態です。こうした言葉から不安がどんどん大きくなっていきますので、意識的に注意してみましょう。

瞑想を続けると勝手に脱フュージョンが起きる
ここまで不安を手放す6つの脱フュージョントレーニングをお伝えしてきました。全部をやる必要はありません。自分の中で効果があると感じたものだけを行えばOKです。
そして最初にも述べましたが、脱フュージョンは瞑想が習慣化されるまでの補助的なテクニックです。瞑想が習慣化されると自分で脱フュージョンを意識しなくても、勝手に不安を客観視する態度が身に着きます。つまり何もしなくても勝手に脱フュージョンが起き続けている状態です。
脱フュージョン自体も有効なテクニックですが、瞑想と併せて取り組むことでより早く不安を客観視できる能力が身に着きます。瞑想の継続も併せてやっていきましょう!
今回のワーク
今回のワークはこちらです。ワークに取り組むことで、このコンテンツを受講して自分がこれからするべき行動が具体化されるようになっています。具体化した行動は毎日の習慣としてください。
