
こんにちは!OPENERSです。
お待たせしました!今回から具体的な瞑想の実践方法を紹介していきますね!瞑想には簡単なものから難しいものまで、数種類があります。最初は簡単なものから紹介していきますので、徐々に日常の中に取り入れていって下さい。最終的にはこれから紹介していく数種類の瞑想を組み合わせて、毎日45分以上瞑想を実践する時間を取り入れてもらうことです。
瞑想は嘔吐恐怖症の克服に役立つだけでなく、他にも様々にポジティブな効果があります。よく適切な「食事」「睡眠」「運動」が人生を豊かにすると言われますが、「瞑想」はここに加えても良いくらい、人生を豊かにする技術です。理想の生活は一日「運動1時間」「瞑想1時間」だと思っているくらいです。
一日45分と聞くと「長いな・・・」と思われるかもしれません。しかし実際に45分はあくまで理想目標であり、一日30分でも15分でも瞑想は効果があります。もちろん長くやるほどに、得られるポジティブな効果も増えていきます。45分は理想的ですが、OPENERS終了時に15分でも瞑想の習慣がつけば、それは大きな収穫だと言えますね。
また瞑想を進めていくとお分かり頂けると思いますが、一日の45分を瞑想に費やしても、全く費用対効果は悪くありません。集中力が高まり、感情にエネルギーを奪われる時間も減り、また瞑想の時間それ自体が高いリフレッシュ効果がありますからね。気づけばお風呂と同じように毎日行わないとスッキリしない感じになると思います!
瞑想の基本

それではまず瞑想の基本からです。瞑想とは「現実を受け入れて、今この瞬間に集中する技術」と紹介しました。この訓練を行うと自分が現実から離れてネガティブ感情に振り回されていることに気づけるので、そういう状態に陥ることが少なくなります。では今この瞬間に起きていること?とは何でしょうか?それは・・・
「呼吸」「体の感覚」「音」「におい」「見えている物」など様々あります。普段考え事をしている時には意識しないようなものです。瞑想では敢えてこれらの「今この瞬間に起きていること」に全ての意識を向けて、それをひたすらに観察します。
今後紹介していく瞑想も全ての基本はコレです。実践時間と意識を向けるものが違うだけです。逆に言えば、今この瞬間に起きていることに集中できているなら、それは全て瞑想の訓練になるわけです。「音楽に没頭する」「見たことない景色を楽しむ」「集中して仕事に打ち込む」ですがいきなり没頭するぞ!集中するぞ!と意識するほどに、できないのが人間です。そのためこの感覚を瞑想によって徐々に養っていくのです。
フォーマルな瞑想とインフォーマルな瞑想
そして瞑想には「フォーマルな瞑想」と「インフォーマルな瞑想」の2種類に分かれます。前者は毎日一定時間瞑想の為だけの時間を確保して実践する瞑想です。後者は日常のふとしたスキマ時間や不安になったタイミングで実践する瞑想です。こちらの方が時間も短く簡単ですから、まずはインフォーマルな瞑想を紹介していきます。インフォーマルな瞑想である程度、感覚が養われてきたらフォーマルな瞑想をお伝えしていきますね!
3分間呼吸法
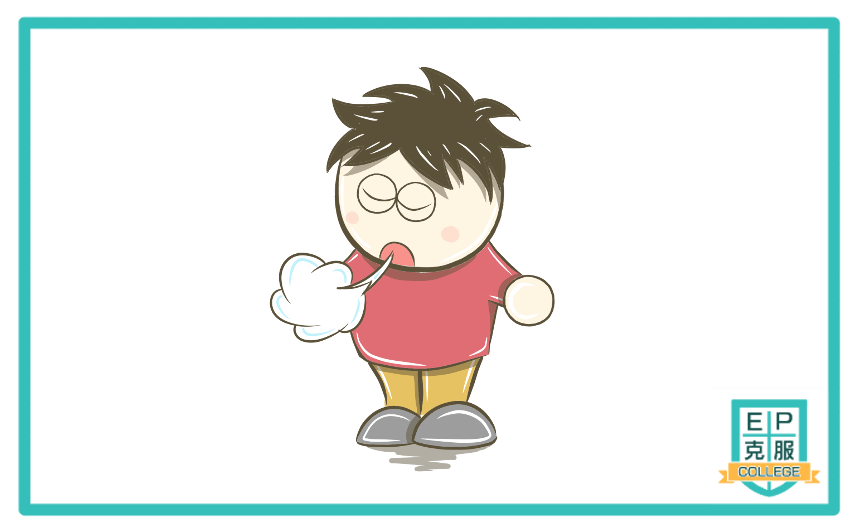
今回は最も基本的な瞑想であり、インフォーマルな瞑想「3分間呼吸法」を紹介します。
全ての意識を呼吸に向ける
3分間呼吸法ではその名の通り「3分間呼吸だけに全ての意識を向ける瞑想法」です。普段呼吸はいつでもどこでも起きていることですから、意識しないと気にも留めないかもしれません。まず背筋を伸ばして、呼吸が通りやすい姿勢を作ります。呼吸は自然に起きるので、鼻から空気が入ってくる感覚、肺が広がる感覚、また空気が鼻から出ていく感覚を全力で感じ取ります。
この間色んな思考が浮かぶと思いますが、瞑想中はその思考について色々と考えをめぐらしてはいけません。思考が浮かぶたび、そのことに気づいて、その度にまた意識を呼吸に戻してあげます。
呼吸を感じ取れる場所は様々あります。鼻先、喉元、胸、お腹、身体全体・・・。呼吸をすると自分がそれを一番感じる場所がありますので、そこに注意を向け続け、感覚を全力で感じ取り続けます。注意を一か所に向けてさえいれば、どの場所に集中しても大丈夫です。
初心者が一番感覚を感じやすいのはおそらく鼻先ですね。鼻先に意識を向けると空気がスッと入って、スッと出ていくのが分かります。この感覚を常に感じ取れるように意識を集中させましょう。
意識がそれるたびに呼吸に戻す
呼吸だけに集中するというのは、たかが3分間でも難しいです。その間も心は色んなことをひっきりなしに言ってきます。「こんな事して何の意味があるの?」「今日は何食べようかな」「仕事が溜まってるな」「不安だな」「寒い」などという思考が次から次へと浮かび、これは止めることができません。
瞑想というと頭の中を空っぽにするイメージでしょうが、現実にそういう状態を維持するのは不可能です。瞑想中はどんな思考が浮かんできても実はOKなのです!思考が浮かんできたことを認め、観察し、また意識を呼吸に戻すことを繰り返すのです。この瞬間に集中力が鍛えられています。
何か考え事に囚われはじめたら、「あ、いけないいけない、呼吸に集中するんだった」とまた呼吸の感覚に集中を戻してください。この集中を戻す時に注意集中力が養われています。筋トレの腕立て伏せで、下した体をまた持ち上げることに相当します。メンタルがどんどん鍛えられているのです。
はじめのうちは3分間の呼吸回数を数えるのも集中を維持する良い方法です。息を吸う時でも吐くときでも良いので、呼吸の数を1から10まで数えます。10になったらまた1から始めます。少しでも集中が切れると数を忘れてしまいますので、正しく数えられていれば良い瞑想となります。
さらにもう少し発展すると、3分間の呼吸で何回自分の注意が呼吸からそれたかを数えるのも良い方法です。余計なことを考えて、また呼吸に注意を戻すたびに数を数えます。10になったらまた1から始めます。
この3分間呼吸法はインフォーマルな瞑想です。日常の中でやってみようと思ったタイミングで実践してみて下さい。電車で一駅移動するとき、不意に不安になった時、嫌なことがあった直後・・・実践してみると自分が現実に反応して、たくさんのネガティブ感情をコントロールの及ばない所で生んでいるのがよくわかるでしょう。一日に3度、計10分程度意識して行ってみましょう!
3分間呼吸法でまず得るもの
3分間呼吸法をやり始めたら、是非身に着けて頂きたい感覚があります。
それは3分間、完全に呼吸だけに没頭し、余計な雑念が一切頭から消えた清らかな状態を経験して頂くこと・・・・・ではありません。
たかだた3分間ですら、余計な思考は止めることができないということを実感して頂きたいのです。
瞑想とは余計な思考を生まなくする訓練ではありません。余計な思考やネガティブ感情は人間の生存機能なので消えることはありません。ただ思考や感情は私達が全くコントロールしていないことを理解するのが目的なのです。
私達は自分が自分の思考や感情を完全にコントロールしているものと思い込んでいますがそうではありません。人間の思考や感情も少し離れてみれば、それは単なる自然現象に過ぎません。自然現象とは基本的に人間がコントロールできるものではありません。
思考をコントロールできると思い込んでいると、ネガティブ感情がやってきたときに「どうしていつもネガティブになるんだ!」という抵抗が生まれます。
ですが思考がコントロールできないものという事実に納得できれば、日々のネガティブ感情も「自分の意志とは全く関係なく自然に沸き上がって来るもの」「それにいちいち取り合って反応する必要は無いこと」が分かります。こうしてネガティブ感情を受け流し、無駄な抵抗をすることも無くなります。そして意識が自然と現実に戻っていくのです。
繰り返しになりますがネガティブ感情がどんどん沸き上がること自体は止められません。瞑想中はただその事実に気づき、感情を認め、観察し、拡大解釈することなく、また呼吸に意識を戻してください。どれほど集中が離れても大丈夫です。その度にまた呼吸に集中を合わせましょう。筋トレと同じでやるだけ効果が出てきます。
症状の悪化を防ぐ3分間呼吸法
3分間呼吸法で呼吸に集中している間は、注意集中力が発揮され感情が暴走することがありません。その間はどのような思考が浮かんできても、冷静に自分を観察している状態を保つことが出来ます。
嘔吐恐怖症の人にとって、一番悩ましいのは「恐怖のスイッチ」が入ることでしょう。
会食中に、お酒を飲んでいる時に、電車に乗っている時に、思いがけなく吐しゃ物に遭遇してしまった時に。気持ち悪さに意識が向いた途端に一気に恐怖のスイッチが入ってしまい、どんどん不安が大きくなってどんどん気持ち悪くなってしまうことがあります。
そんな時に無理に感情を抑え込むという方法しか知らないと、どんどん感情が暴走して症状も悪化してしまいます。ですがこんな時に呼吸法はとても役に立ちます。
恐怖のスイッチが入ってしまったら、まず呼吸に意識を向けましょう。 呼吸法をすることで、一気に不安が大きくなるのを防げます。症状が悪化するのも防げます。呼吸法をするとは言わば私達の感情が暴走しないセーフモードに入るようなものです。
普段から3分間呼吸法を練習して、セーフモードに入れるようにしておくと、恐怖のスイッチが入ってしまうことへの不安もなくなっていきます。嘔吐恐怖症の症状をダイレクトに緩和できる方法ですので、是非練習していきましょう!
コレだけはやろう
まずは一日一回3分間呼吸法やってみましょう。
全ての瞑想の基本~呼吸
今回は呼吸に集中する瞑想法を紹介しました。しかしこの後紹介していく瞑想も集中する対象は呼吸が基本になります。(他の対象にも注意をむけますが、思考がさまよいだしたら一度呼吸に集中を戻すというステップがあります。)そのため3分間呼吸法は最も取り組みやすい瞑想ではありますが、最も重要な奥が深い瞑想でもあります。
野球やテニスの素振りなど、スポーツでいう所の基礎反復練習にあたるでしょう。ここでしっかり呼吸に集中する感覚を身に着けておくと、その後の瞑想もスムーズに入ることが出来ますので、是非真剣に取り組んでみて下さいね。
瞑想へのグラウンドルール
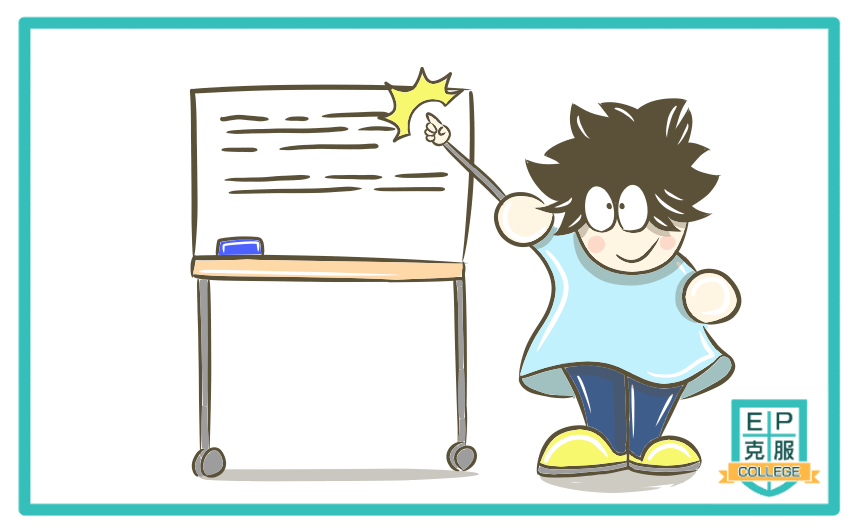
瞑想を実践してみると分かりますが、最初のうちはさまざまに意識の反発が起きます。ここでは挫折せずに瞑想を続けて頂けるように、瞑想に対する基本的な態度を紹介しておきます。瞑想には以下の態度が重要となります。もし瞑想がうまくいかないと感じたらこの基本に立ち返ってみて下さいね。
- 自分では評価を下さない
- うまくなろうとしない
- 全てを受け入れる
- 実践が全て
- 鼻うがいのススメ
ルール1:自分では評価を下さない
新しい習慣として瞑想を始めた!早く成果が欲しい所ですよね?しかし間違えてはいけないのは瞑想を行えばネガティブ感情が生まれてくることが無くなる訳では無い、ということです。もしそんなことができれば、その人の人格そのものが無くなってしまうに等しいです。
そうではなく瞑想で身に着くのは注意集中力であり、自分がネガティブ感情に囚われていることに気づき、認め、そして注意を自分が今取り組んでいることに向ける力です。ネガティブ感情を消すのではなく、受け入れて受け流すの力が身に着くのです。
こうした力は自分ではなかなか実感できないものです。そのため瞑想でどれくらいの成果が出ているか?というのを推し量るのも難しいものです。ですが続けていれば、ふとした瞬間に「あれ?今湧いてきた不安が気づいたら無くなっていた」という体験をするようになります。早くに結果を求めすぎると、「期待通りの効果が出ない!」と間違った評価をくだしてしまい、挫折の原因にもなってしまいます。
やり続けていればポジティブな効果は出ますので、自分では結果の評価を下さないようにしましょう。ただやり続ければそれで良いのです。
ルール2:うまくなろうとしない
最初からうまく瞑想が出来る人はいないですし、そもそも瞑想とは上達するものではありません。上達するというよりも、体験するという表現が正しいです。
瞑想を始めると、全く集中できないこと、瞑想になっていないと感じることがたくさんあります。本日紹介した3分間呼吸法でさえ、3分間ほとんど集中できずに終わってしまうこともあるでしょう。こうなると「自分には全然瞑想がうまくできない!」と感じるでしょうが、ですがそれで良いのです。瞑想とは注意集中力の維持時間を延ばすことではなく、注意集中力がそれて、さまよいだしたら、また呼吸に集中を戻すことに効果があります。
つまり瞑想中にはどんなに思考がさまよって、集中できなくてもOKなのです。そのたびに「あ、また呼吸に集中しよう」と戻ってくることが大事なのです。思考がさまようほどに良い瞑想の練習が出来るというわけです。もし3分間呼吸法の間に100回思考がさまよいだしたら、それでもOKです。そのたびに呼吸に集中を戻しましょう。
仮に全く思考がさまよわない状態を瞑想上手と言うならば、そういう状態を目指しているのでは無いですね。うまくなる必要はありませんし、また好きになる必要もありません。ただやり続ければそれで良いのです。
ルール3:全てを受け入れる
瞑想を始めると上記のような結果を求める態度や、瞑想がうまくできない自分に対する批判的な態度、瞑想に対する懐疑的な態度など様々に生まれてきます。さらに過去や未来やセルフイメージに対するネガティブ感情が湧きおこってくることもあります。しかしそういった態度や感情も含めて受け入れ、また呼吸に集中していくというのが大切になります。
私たちはついつい「どうしてこんな感情が生まれるんだ!」と良い感情、悪い感情とレッテルを貼り、判断を下し、良い感情だけが生まれてほしいと望みます。しかしこれまで学んできたようにネガティブ感情を止める方法もコントロールする方法もありません。そもそも生まれてきてはいけない感情というのは存在しないのです。どんな感情でも必ず私たちの生存に寄与するから存在するのです。
瞑想中にネガティブ感情が生まれると、「自分は瞑想がうまくできない」「ネガティブ感情につかまってしまう」というネガティブ感情からうまく脱せないことに対するネガティブ感情も生まれてくると思います。ですがそういった感情も誰しもが抱える避けることが出来ないものです。自分が好まない感情が生まれてきても、それに判断を持ち込まず、ただ呼吸に集中して、感情が変化し消え去っていくのを観察してください。
繰り返しになりますが、生まれてきてはいけない感情はありません。瞑想は全ての感情を受け入れ、観察し、また呼吸に意識を戻すの繰り返しです。どんな感情も受け入れる訓練なので、強い感情に襲われた時でも、いつでも心に平穏を取り戻せるようになるのです。
ルール4:実践が全て
これは瞑想に限らずですが、心理技術というのは効果を生理学的なメカニズムの観点から証明することが出来ません。例えばある病気であれば「体のどの部分が不調で、どういう物質の分泌が減って、どういう症状が出るか」と証明することが出来ます。だから病気に対する薬も開発できるわけです。
心理技術にはこのようなメカニズムの証明がありません。心理技術というのは脳のニューロンの配線をつなぎ変えているようなものですから、それをメカニズムとして証明することは(今の人類には)不可能なのです。
ただ分かっているのは「瞑想をすると不安が減って、うつ病やパニック障害が良くなる」ということだけです。理由は分からないが、とにかく瞑想をすればポジティブな効果があることが分かっているのです。実践が全てという訳です。
さらに瞑想をやり始めると、もっと瞑想をうまく行う為の「知識」を身につけたくなります。呼吸の数を数えたりするのは知識の一つです。しかしいくら知識を身に着けても、それを自分で実践して体験していかなければ意味はありません。
私自身も瞑想については、その方法についてかなり調べてきましたが、具体的な実践の部分になるとあまり多くの情報は得られませんでした。「とにかくやってみれば分かる」というものがほとんどです。
瞑想は身に着けるべき「知識」はあまり多くありません。このOPENERSでお伝えする内容で十分です。瞑想を上手くなるために、あれこれ調べたり勉強したりする必要はありません。そんなことよりもまず3分間呼吸法を続けてみることの方がよっぽど大事です。 とにかく実践していきましょう!
ルール5:鼻うがいのススメ
こちらはルール?ではありませんが、瞑想を始めたら鼻うがいも始めてみることをオススメします。
鼻うがいはご存知でしょうか?鼻うがいは鼻の通りを良くして、呼吸をスムーズにしてくれます。瞑想の前に鼻うがいをすると、楽に呼吸を感じ取ることが出来るので是非オススメします。
薬局に行けばセットが売っています。また鼻うがいは痛いというイメージがありますが、うがいはただの水では無く自分でも作れる生理食塩水で行いますので、少し慣れてしまえば全然痛くありません。
以上が瞑想の基本的な態度になります。うまくいかないと感じたらここに立ち戻ってみて下さいね。それでは今日から3分間呼吸法を実践してみましょう!一日に3度、計10分程度意識して行ってみましょう! 次回は別のインフォーマルな瞑想を講義したいと思います。
今回のワーク
今回のワークはこちらです。ワークに取り組むことで、このコンテンツを受講して自分がこれからするべき行動が具体化されるようになっています。具体化した行動は毎日の習慣としてください。
今回は2枚のワークです。
